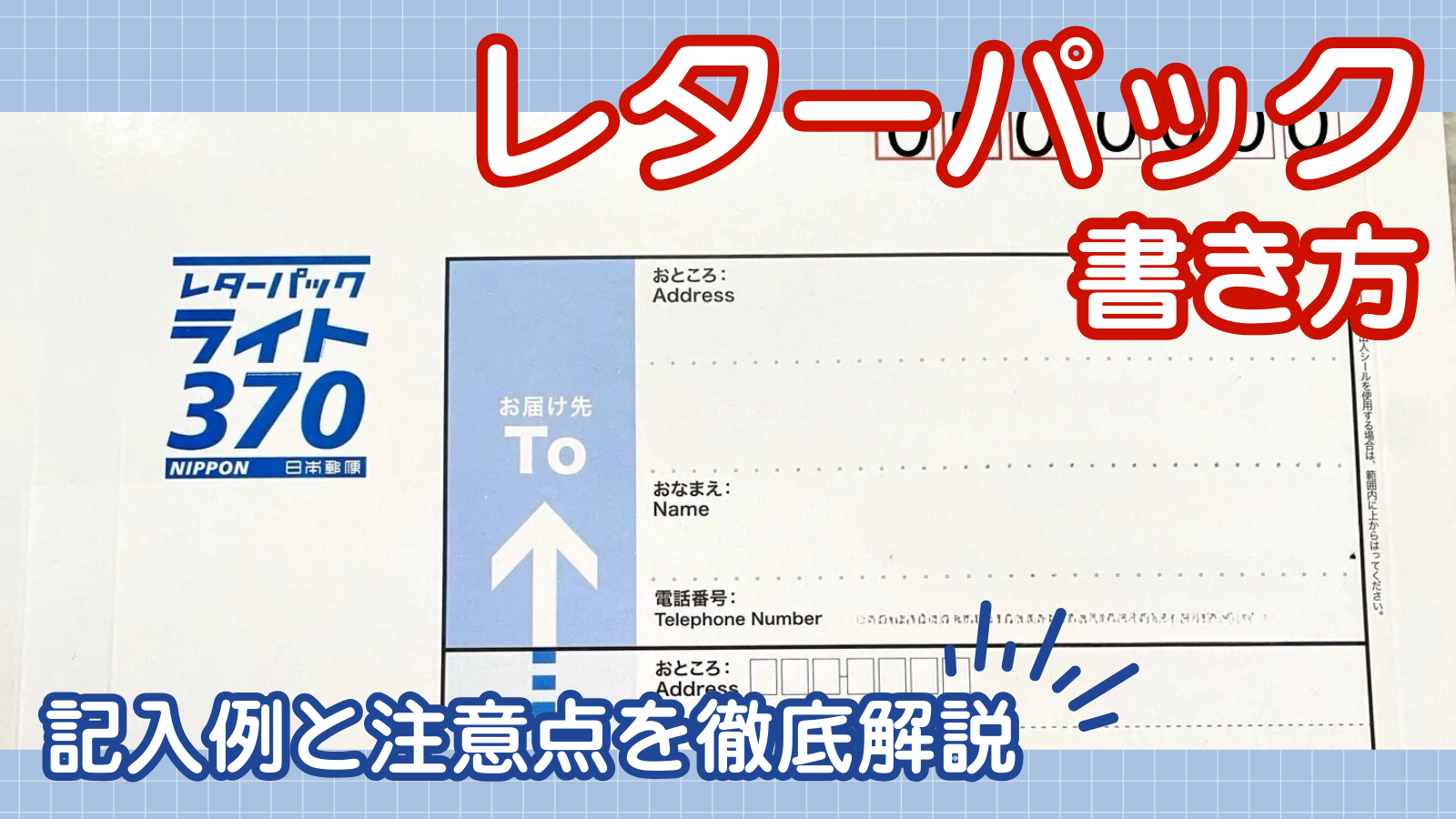おもちゃの断捨離なんて本当に可能…?子供の納得を得つつ進めるコツ
子供のいる家庭では、毎日あっという間に散らかるおもちゃに悩んでる方が多いと思います。
まして、男女の兄妹であったり、同性でも年の離れた兄弟では遊ぶおもちゃが違いますし、誕生日やクリスマスなどの度に、おもちゃの量は何倍にもなってしまいがち。
使わないおもちゃは断捨離をして捨てたいけれど、何をどう捨てたらいいか分からない!ということはないでしょうか?
おもちゃを勝手に捨てて、あとで「あのおもちゃがない!」「なんで捨てちゃったの!」と大騒ぎになることのないよう、子供も納得しておもちゃを処分できたら理想的ですよね♪
ここでは、おもちゃの断捨離について詳しくお話していきたいと思います。
大人が勝手におもちゃを捨てない

おもちゃの断捨離は、子供にとって大切なおもちゃの選別ですので、大人主導ではなく、子供と一緒に断捨離を進めていくことがおススメ!
大人には使っていないガラクタに見えるものであっても、子供にとっては大切なものの場合があり、子供の物に対する価値観は、大人や親が勝手に決めつけてはいけません。
とはいっても、破損や故障したもの、年齢に合わないおもちゃは断捨離して破棄します。
「これは動かなくて使えないね」など理由も子供に伝えて、納得してから破棄すれば、あとで子供の心が傷つかず、断捨離はスムーズに進みますね。
断捨離は、おもちゃを仕分けしながら物の大切さや、選び方、片づけを子供と一緒に教えて、考える力を学べる絶好のチャンスなんです。
我が家には、8歳、5歳、3歳の子供がいますが、物心ついた頃から定期的に「いる?いらない?」と尋ねて子供が決める形で断捨離するようにしています。
現在では、上の子は自分で断捨離や片付けができるようになって、下の子もそれを見ているので自然とできてきています。
また、破棄する際には、「少し乱暴に扱ったから壊れてしまったね。今度からはもっと大事に遊ぼうね。」「今までありがとうだね。」など物の扱い方や物の大切さも子供に伝えましょう。
おもちゃは子供が自分で片付けしやすく

細かくこれはココ!と指定席を決めるのもいいですが、子供にとっては難易度が高く、片付けが面倒になってグチャグチャになりがち。
子供にとって、取り出しやすく片付けしやすい収納にするには、取り出しやすい高さに置いて、ワンアクションで出し入れができること。
そして、大きいボックスに「車だけ」「人形だけ」と1種類ごとにおもちゃを収納すると子供にも分かりやすく片付けをすることができます。
そして、そのボックスの外側には、写真やイラストなどで何が入っているかわかりやすくしておいて、おもちゃはこのボックスに入る分だけと量を決めておくことも大切。
入りきらなくなったら、収納を買い足すのではなく、断捨離でおもちゃを見直してみましょう。
おすすめ
[PR]

おすすめ
[PR]

子供とおもちゃの断捨離のやり方





おもちゃは破棄しない方法もアリ!

「いらない」と子供が決断したおもちゃの中には、まだまだキレイで使えるものがありますよね。
そんなおもちゃは、破棄しなくても誰かに譲ったり、リサイクルショップやフリマアプリなどで売ったりすることもできます。
下の子が生まれていたり、いずれ出産を計画しているなら、キレイなものは保管しておくことも考えると思いますが、おもちゃは数年たつと古くなったり、劣化することもありますので、厳選して保管します。
全て取っておかなくても、下の子がおもちゃを必要な時に、必要なものをフリマアプリなどで安く購入することもできるます。
場所を取って保管するか、再度購入するか検討しましょう。
保管する場合には、使っていたおもちゃは隅々までアルコール除菌でキレイにした状態で、カビなどが生えないよう湿気のない場所で保管をしておきましょう。
まとめ
おもちゃの断捨離は、大人が勝手に行うことはせず、子供に破棄の決定権を渡して、一緒におもちゃを選別していきましょう。
子供主導で思うように断捨離が進まなくても、時期が来れば自然と手放せる日が来ます!
無理せず楽しんで、おもちゃの断捨離をしましょう♪