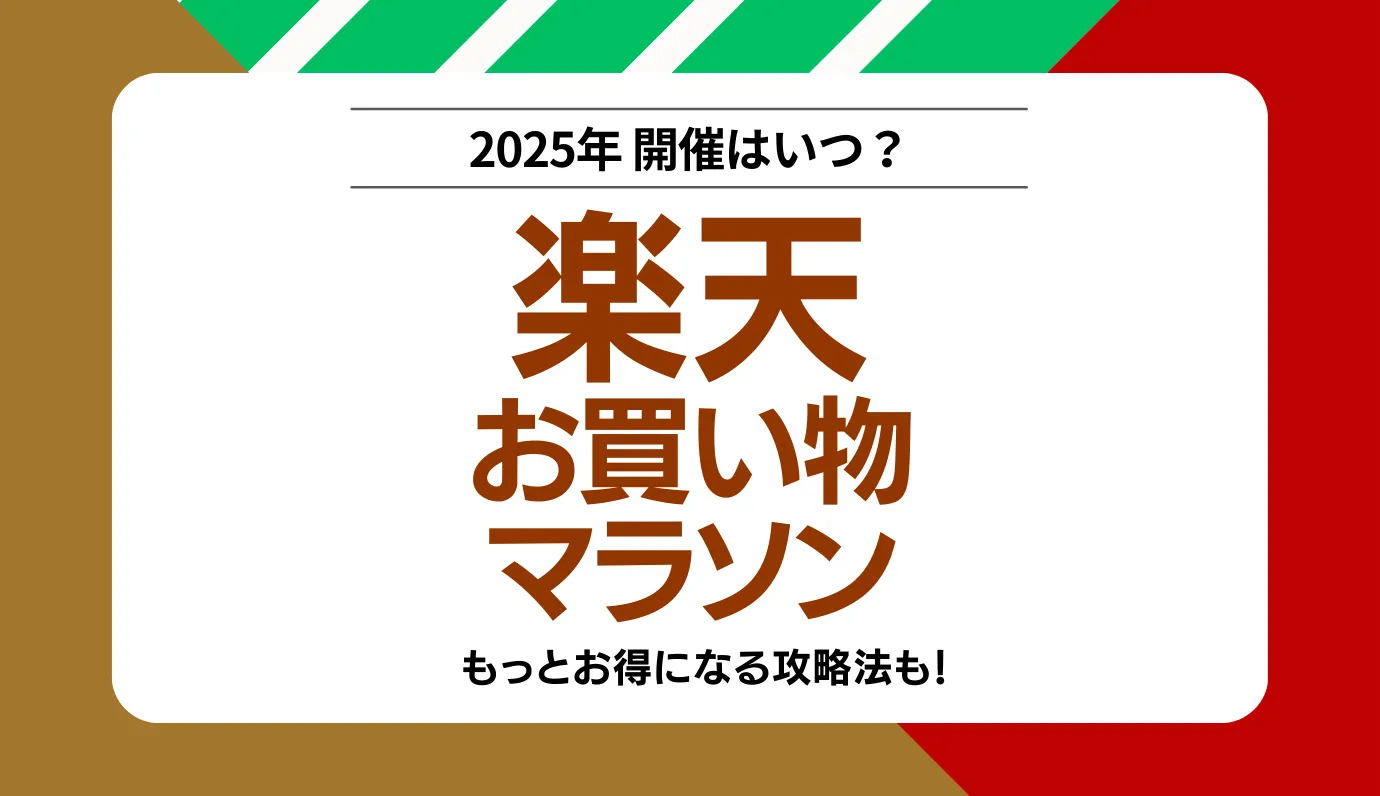靴底の修理は簡単にできる!すり減りや剥がれを補修する方法
歩いていたら足に違和感が。靴の裏を見てみたらボロボロだった…という経験、ありませんか?靴の表面は気にすることがあっても、底は気にしていない人が多いかもしれません。でも靴底って、すり減ってきたり剥がれてしまったり、気づかないうちに傷んでいることが多いんです。実は、靴底の修理は自分でもできちゃうんですよ!プロにお願いした方が良い場合もありますが、せっかくなら大切な靴を自分の手で補修してみませんか?ということで今回は、靴底の補修の方法を紹介していきます。
本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています
目次
靴底はどうなったら修理が必要?

靴底の修理、といっても、そもそもどこを修理する必要があるのか、なんで修理する必要があるのかわからない人もいるかもしれません。ということで、ここでは靴底の中でも、どの部分がどうなったら修理が必要なのかを見ていきましょう。
靴底と一口に言っても、ヒールの部分やつま先の方の底など、修理した方がいい場所は細かく分かれます。
ヒール部分のすり減り
ずっとその靴を履いて歩いていると、ヒールのすり減りは避けられません。この「ヒール」というのは、女性用のピンヒールだけではなくて、男性が履く革靴などの場合も同じです。
そこで必要なのがヒールのゴム部分の交換。交換せずに放っておいてしまうと、滑りやすく、危険です。
特に女性用のヒールの場合には、中の金属がむき出しになってしまうことがあります。そうなると、歩くたびにカツカツ音が鳴ってしまい、うるさい…!なんてことにもなってしまいます。女性靴の場合も男性靴の場合も、すり減ってきたら、ゴムの交換が必要です。
前底のすり減り
前半分の靴の底も、だんだんすり減ってきます。この部分がすり減ると、やはり滑りやすくなってしまって危険です。すり減ってきたと思ったら、早めに交換してください。また、この部分を交換すると、ゴムの厚みが出ることでクッション性も増すので、歩きやすくなるというメリットもあります。
全体がベロンと剥がれてしまっている
これはさすがに修理しなきゃだめだってことはわかりますよね!歩いている最中に剥がれてしまって、ちょっぴり恥ずかしい思いをしたことがある…なんて人もいるかも?
靴底がゴムでできている靴の場合は、このように靴底がベロンと剥がれてしまう可能性が高いです。
ゴムは、雨や紫外線に弱いのです。ゴムは濡れてしまうと、加水分解という化学反応を起こして、剥がれやすくなってしまいます。また、紫外線にずっと当たっていると、酸化してゆがんだり、ひびが入ったりと、劣化しやすいのです。
ちなみに、ヒールと前底のすり減りは、革靴やパンプスによく見られます。全体の剥がれは、ゴムでできたソールの靴に多いので、スニーカーによく見られます。
ここまで靴底で修理した方がいい場所を紹介してきました。でも必ず靴修理のプロに頼まなくちゃいけない、というわけではありません。実は自分でできちゃうんです!
ヒール部分のゴムの交換を自分でする

ヒールがすり減ってしまうのは、革靴やパンプスです。フォーマルな場で使うことも多いアイテムだからこそ、きちんときれいなヒールにしておきたいですよね。
・新しいヒール部分
・トンカチ
・接着剤
・紙やすり
新しいヒールのゴム部分は、100均や靴修理のお店で買うことができますよ。もし他のアイテムが家にそろっていれば、補修費用を抑えられますね。
方法を簡単に説明すると、古いゴムをペンチなどで取って、そこへ新しいヒール部分をセットする、という感じです。セットしたら、トンカチか接着剤でしっかりとめていきます。
詳しいやり方は、この記事に写真付きで解説しているので、ぜひ読んでみてください。
前底の修理は職人に頼むのがおすすめ

続いて前底のすり減り。すり減りができやすいのは、革靴やパンプスです。
ここでちょっと注意。靴底の修理は自分でできる!と言いましたが、前底の場合はおすすめはできないのです…。前底の修理はもしかしたら職人さんに頼んだ方がいいかもしれません。
一応、自分でできなくはありません。自分で補修したい場合には、靴修理のお店などで、このようなアイテムを用意しましょう。
おすすめ
(PR)
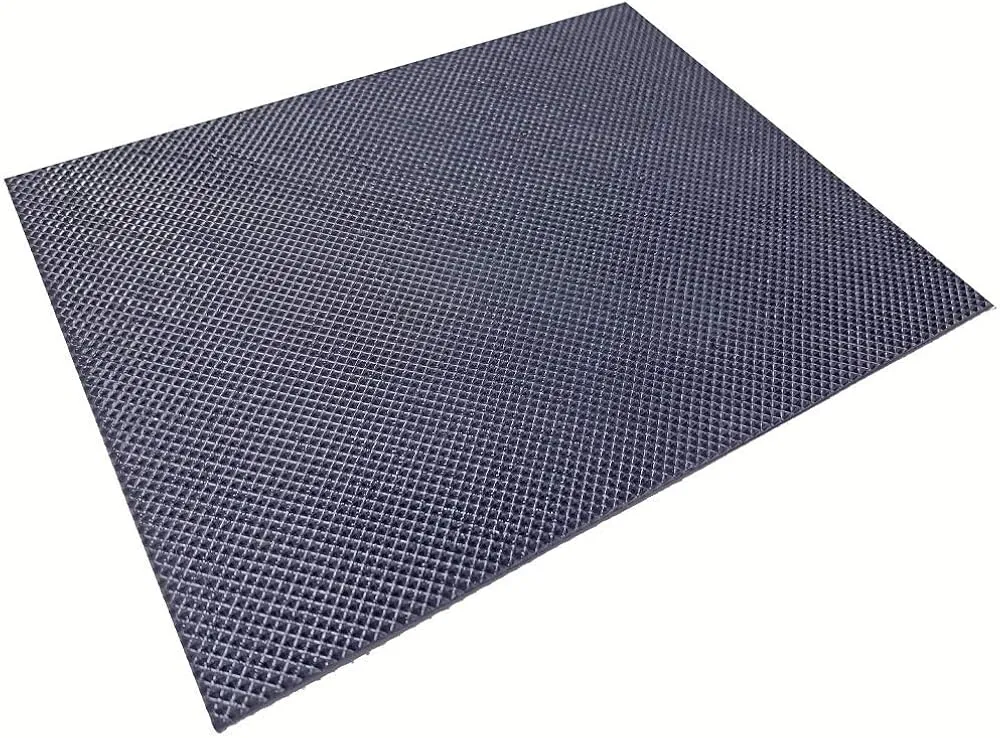
これを前底に貼り付けて、補修します。
ただ、やっぱり自分で貼り付けるだけだと、剥がれてしまいやすくなってしまいます。いつか剥がれてしまうのではないかと不安になりながらのお出かけなんて全然楽しくない!それに、革靴やパンプスのようにフォーマルな場で身に着けることも多いと、剥がれてしまったら、結構恥ずかしいことになってしまうかもしれません…。
ということで、前底の修理は靴修理の職人さんに頼んでしまうのがおすすめ!ちなみに、前底のことは「ハーフソール」といいます。ハーフソールの修理は、職人さんならきれいに仕上げてくれますよ。
プロの技はこの記事で確認してみてください。この新品のような仕上がりは、職人さんならではです。
あわせて読みたい
ベロンと剥がれてしまっているなら接着剤かネジを使って

ベロンと剥がれてしまう靴はスニーカーが多いです。スニーカーのソールはゴムでできているので、どうしても剥がれやすくなってしまっているんですよね。
正直なところ、できればこの剥がれもプロに任せた方が良いです。でもスニーカーだったら、割と気軽に自分で補修することができるんじゃないかな、と思うので、方法を説明していきます。
方法は、接着剤を使う場合と、ネジを使う場合の2種類あります。
接着剤を使って修理する
まず簡単なのは接着剤を使う方法。とはいっても、普通の瞬間接着剤を使うのではありません。靴専用の接着剤が売られているので、そちらを使うことをおすすめします。ポリウレタン、合成ゴムと靴本体をくっつけるのは、靴専用の接着剤の方が適しているんです。
おすすめ
(PR)

靴用の接着剤。固まるとゴム状になる接着剤なので雨に強く、透明になるため、はみ出してもあまり目立ちません。また、塗ってから小さい部分だと1時間で乾きます。大きい部分でも24時間置いておくと乾くので、翌日から履くことができるんです。
・靴用接着剤
・ヘラ または 割りばし
・ハンマー
・重石になるもの(いらなくなった雑誌など)
・はさみ

まずは新聞紙を敷いて作業を開始しましょう。作業スペースを確保できたら、接着剤を塗ります。
接着面のどちらか片面だけでなく、靴本体と靴底の両面に接着剤を出します。ヘラや割りばしで全体に伸ばしましょう。

接着剤を塗て、すぐに貼り合わせるのはNG。そのまま5分ほど置きましょう。ただ、接着剤のパッケージに貼り方が書いてある場合は、説明に従ってください。

しばらく置いたら、接着剤を塗った靴本体と靴底を貼り合わせます。貼り合わせたら、ハンマーで靴底から叩くことでしっかりと密着させます。
その後、靴の上からいらなくなった雑誌などの重石を置いて、1時間ほど放置して接着剤を乾かします。ただ、この場合、デリケートな革靴などは重石でシワなどが入ってしまい傷む原因になってしまうため、そのまま乾かしましょう。スニーカーなどの場合でも、中に丸めた新聞紙などの詰め物をしてから雑誌などを乗せて乾かしましょう。
接着剤が乾いたら、接着面からはみ出た接着剤をはさみで切り取ります。これで完了です。重要なのはしっかり密着させること!
ネジを使って補修してみる

接着剤による補修は、もちろん効果があります。しかし、やはり水に触れたり時間が経ったりで再び剥がれてしまうことが多いのです。そこで、接着剤よりも強力に靴底を靴にとどめておく方法があるんです!
それはネジで固定させる方法。 ただ、この方法は、靴底が薄かったり柔らかかったりするものには、適していません。だって、ほら、ネジが飛び出たり穴が広がってしまったりするでしょ?注意してくださいね。靴底が分厚くてかたいブーツやスニーカーでやってみましょう。それでは、ネジで補修する方法をご紹介します。
・ドライバー
頭が平たいネジのこと。靴底の厚さにもよりますが、10mmが飛び出ない程度の長さでおすすめです。
靴の内側からネジを打ち込むため、靴ひもをほどいて中敷きを取り出します。

ドライバーで靴にネジを打ち込みます。かかとの部分と、つま先の近くは打ちにくいですが、できるだけ奥の部分に、靴底をしっかり固定した状態でネジを入れていきます。
つま先とかかと、それぞれ3本ほどで十分です。打ち込んだら、ネジが靴底から飛び出ていないか確認しましょう。
安全が確認できたら、中敷きを元に戻して完了です。
たったのこれだけ。接着剤を塗った後にこの作業をすると、ぴったり貼りつくのでおすすめですよ。
ダイソーの商品で靴底を補修!

修理にお金をかけていたら、意外な金額に!思い入れのある一足ならいいのですが、買い換えた方が安いなんてことも。そうなるのを防ぐためにも、100均をうまく活用して修理しましょう。
今回ご紹介するのは、100均のダイソーの商品。便利なアイテムを数点ピックアップしたので、順を追って説明していきます♪
また、前底はプロに依頼した方が無難だとお話しましたね。なので、ここではヒール部と剥がれの2点に絞ってご紹介していきます。
ヒール部用 修理アイテム
・靴底修理材 2足分4個セット
ヒール部修理に使うゴム板。110円という安さで4個も入っているので、2回修理に使えますね。片側だけすり減ってしまう人なら、4回も修理できちゃう!
専用のクギも同封されているので、修理方法はさっき上で紹介したやり方でOK。注意点をあげるなら、これ以外にも道具が必要なこと。
2.カッター
3.接着剤
具体的に上げるとこの3点です。それ程難しい道具でもないので、すり減り具合に合わせて修理材を選んでいきましょう。
・靴底修理材 夫人かかと用 4個セット
ハイヒール系の靴底修理に使えるタイプもあります。こちらも同じく4個セットなのですが、ゴムにピンが付いています。
ご存知の方もいるかも知れませんが、ハイヒールのヒール部は取れるんです。なのですり減ったヒールが気になった方は、ペンチで引き抜いてこちらを挿すだけ。意外と簡単ですよね。
厳密には余分なゴムを切ったりするのですが、その程度です。穴のサイズが合わない時も、ゴム片を詰めることで解決できます。知らなかった方も、一度修理に挑戦してみましょう。
・紙やすり
こちらはおまけですが、紙やすりもダイソーに売られています。目の粗さも選べるので、荒削り用と仕上げ用を買っておくのがおすすめ。段々目の細かいやすりで削っていくと、仕上がりがきれいになりますよ♪
剥がれ用 修理アイテム
・靴底補修用(ボンド)
先程紹介した接着剤もいいのですが、試しに行う修理なら100均のもので十分でしょう。少し剥がれた靴底を貼り合わせるのはもちろん、ヒール部補修にも使いましたね。
また、この他にもいくつか使用方法が。少し穴の開いてしまった部分に付けて塞いだり、減りやすい部分に付けてガードしたり。応用次第でいろんな使い方ができるのも魅力的です。プロの修理には及びませんが、応急処置としても使えるのでぜひ買っておきましょう。
まとめ
靴底は、見えないようで、意外と人からは見えていたりします。こういう細かいところまで気を配れるような人になりたいですよね。そのためにも、いつも履く靴の底はチェック。ちょっと補修が必要かも…と思ったら、ぜひここで紹介した方法で直してみましょう。でも前底の補修は、プロにお任せを。大切に、長く靴を愛用していくためには、しっかりとメンテナンスすることが肝心です。
※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。
※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。
※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。
※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。