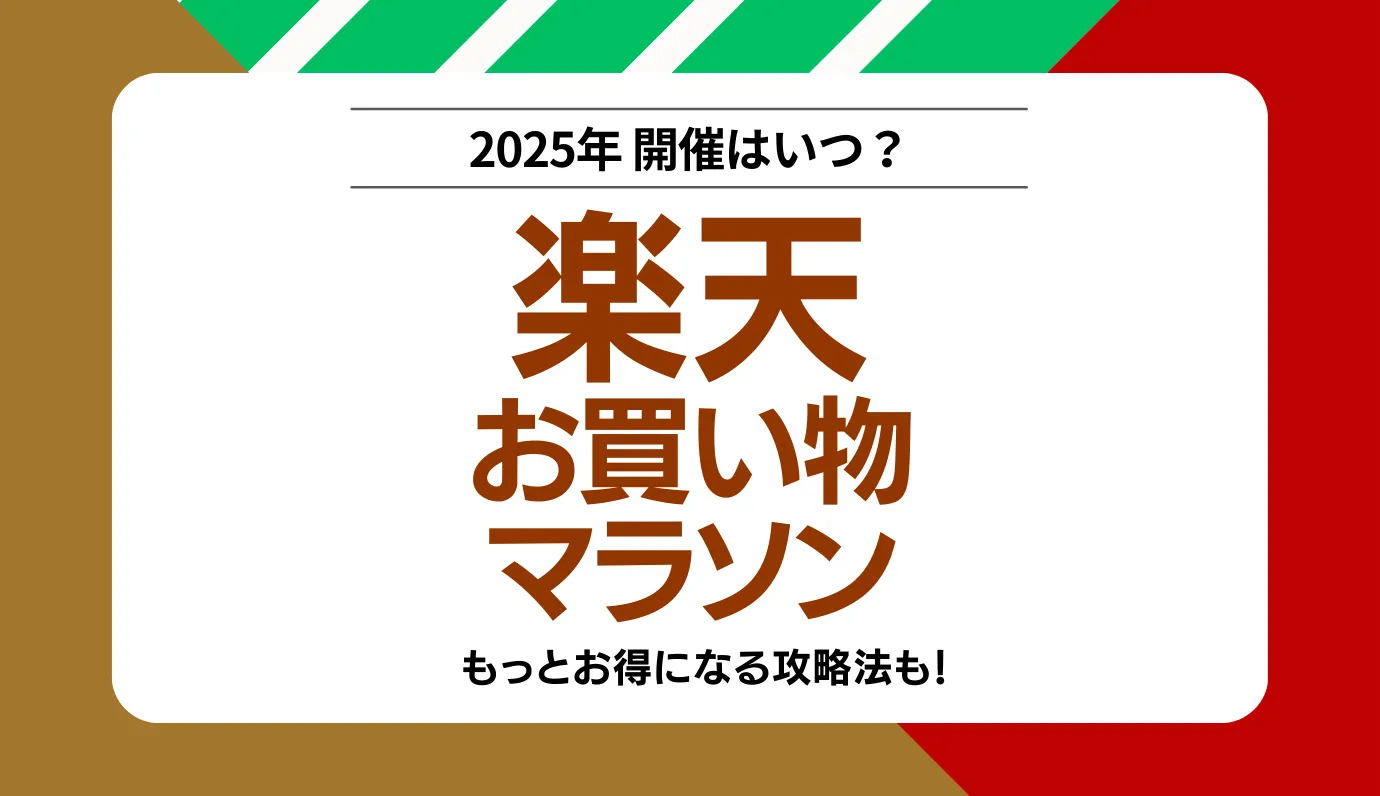【服の虫食い対策】防虫剤だけは不十分?予防法から衣服の収納法まで徹底解説
洋服を収納から取り出すと穴が開いていることはありませんか?それは虫食いサインの可能性があります。収納に防虫剤を入れるだけではなく、衣類害虫が住みにくい環境を作ることも大切です。本記事では虫食いを防ぐために気をつけたいポイントを解説。しっかり対策してお気に入りの服を長く着られるようにしていきましょう。
本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています
目次
服の虫食いの犯人は…!?

気になる虫食いの犯人…それは、甲虫の「カツオブシムシ」と、蛾の「イガ」の幼虫です。5mmに満たないほどの大きさのため、肉眼で見つけることは至難の技。
これらの虫の中でも特に多いのが、カツオブシムシの一種である「ヒメカツオブシムシ」と「ヒメマルカツオブシムシ」です。その幼虫の食べ物は、繊維やホコリ。成虫やさなぎは衣類を食べることはありませんが、成虫は衣服に卵を産み付けます。
また、クローゼットやタンスの中に細長いゴミが落ちていると思い、よく見てみるとさなぎの抜け殻だった…という恐ろしい経験をしたことがある方もいるかもしれません。
家の中は暖かいため、虫にとって居心地がいいことから、幼虫の期間を経て成虫になっても外に出て行かず、家の中で暮らし続け、何世代も続いていくこともあるんです。
服の虫食いの犯人はどこからやってくる?
成虫は屋外のあらゆるところで飛び回っており、外を歩くだけで衣服にくっついたり、屋外に干している洗濯物に集まったりして産卵します。光に集まりやすい習性があるので、特に白い服は要注意です。
害虫が活動する場所は?
害虫が好む環境は、以下の3つが揃っている場所です。
・湿度:60~80%
・栄養:ホコリ・繊維・タンパク質がたくさんあるところ
暑すぎずジメジメしていて、汚れた場所ということですね。湿気がたまりやすい服が入ったタンスやクローゼットは、害虫にとって楽園。虫を防ぐには、ここをいかに対策するかがポイントになってきます。
どんな服が虫食いされやすい?
・植物性繊維(綿・麻)の服
繊維にはさまざまな種類がありますが、害虫に好まれるのは動物繊維。ウールやシルクが当てはまります。また、綿や麻などの植物性繊維を好んで食べる種類もいます。
さらに、動物性繊維や植物性繊維の服と重ねて置いたり、食べこぼしや皮脂で汚れたりしている場合は、化学繊維のポリエステルやレーヨンでも虫食いの被害に遭うことがあります。
食べこぼしなどの服についた汚れは、しまう前にきちんと洗っておいた方がいいんですね。
大切な服が虫食いに遭ったら「かけはぎ」を駆使する
もう食われてしまった…というときは、クリーニングや衣類リフォームで「かけつぎ(かけはぎ)」という方法で穴を塞げる場合もあります。これは破れて穴が開いてしまった生地を、周りの繊維を取り込みながら元の状態に近づけていく再生技術のこと。この技術を専門にしている業者もあります。
虫食いにあった衣類を再び着たい際は、この技術で再生できるかもしれません。でも、どうやってお店を見つければいいの?そんなときはユアマイスターにお任せください!
防虫剤の前にやっておきたい服の虫食い対策

防虫剤は、その字の通り「虫を防ぐ」薬剤です。防虫剤は寄せつけないだけで、退治わけではないのです。すでに虫が入り込んでいるタンスやクローゼットに使っても、害虫を根絶やしにできるわけではなく、追い出した幼虫や成虫が他の場所に移って、そこから新たに繁殖を始めます。
まずは害虫を家に持ち込まない、しっかり退治する、害虫を寄せ付けない環境づくりをする。これが大事になってきます。それでは、防虫剤を入れる前にやっておきたいことを紹介していきます。
洗濯物を取り込むときや帰宅したときは手ではらってから
成虫は屋外のあちこちにいるので、卵を産みつけようと服に集まってきます。そのため卵や成虫を家に持ち込まないために、洗濯物を取り込む前や家に帰るときは、服を手ではらってから取り込むようにしましょう。花粉を落とす効果もありますよ!
タンスにしまう前に洗濯やクリーニングで汚れを落とす
害虫は皮脂や食べ残しが大好物のため、服が汚れたままタンスにしまうと食べられてしまいます。そのため、特に衣替え前には可能な限り洗濯やクリーニングで綺麗な状態にしましょう。
ニットやセーターの洗濯方法はこちらの記事をチェック!自宅での正しい洗濯法や干し方も載っています。
あわせて読みたい
アイロンをかける
洗濯が終わったら、今度はアイロン。害虫は熱に弱いので、アイロンがけにより退治できる可能性が高まります。シワも伸ばせるため、服の保管前には大切な工程です。
除湿剤を使用する
害虫はジメジメした場所が大好き。洋服は湿気を吸い込みやすいので、クローゼットには除湿剤は必須です。カビを防止するためにも、除湿剤を活用しましょう。
おすすめ [PR]

吸湿量が多い置き型タイプの除湿剤ならこちらの商品を!ハサミを使わず、シールを剥がすだけで簡単にたまった水を捨てることができます。
おすすめ [PR]

ハンガータイプの除湿剤でおすすめなのがこちら。衣服と衣服の間に吊り下げるので、服の湿気を素早く吸収してくれます。また、置き型タイプに比べて表面積が広いので吸湿スピードが早いですよ。
クリーニング後のビニール袋は外す
クリーニングに出した服はビニール袋にかぶさって返ってきますよね。ホコリがつかないようにつけたまま収納している方も多いかと思いますが、実はビニールは外すのが正解です。
その理由は、ビニールがついたままだと空気の循環が悪くなり、熱や湿気がこもりやすいから。それだけでなく、服が変色したり、臭いを吸収しやすくなったりしてしまう可能性があるので、必ず外してから収納するようにしましょう。
服の虫食いを防ぐために防虫剤を使う際のポイント

それではいよいよ防虫剤の出番です。防虫剤は、ガスを発生させて虫を寄せ付けないようにするものです。このガスがきちんと空間に行き渡るようにしないとちゃんとした効果が得られません。このことを念頭において、ポイントを解説していきます。
防虫剤は場所別に設置を!
防虫剤には引き出し・衣装ケース用、洋ダンス用、クローゼット用など、使いたい場所に合わせた商品が揃っています。それぞれの収納空間の広さに合わせて、ガスが適度に行き渡るようになっているので、使いたい場所に適したものを選びましょう。
おすすめ [PR]

おすすめ [PR]

おすすめ [PR]

ムシューダは場所別に様々な種類を取り揃えています。ここでは「引き出し・衣装ケース用」「クローゼット用」「ウォーキングクローゼット用」の3商品をピックアップ!1年間有効で、取り換えの時期には「おわり」といった文字が浮かび上がるので、一目でわかるようになっています。
防虫剤を服の上に置く
防虫剤の成分は空気よりも重いため、上から下にガスが浸透していきます。収納ケースを使用する場合は、服の下に置くのではなく、畳んだ服の上に置くようにしましょう。また、服を重ねて入れるとガスが下の服まで行き渡らない可能性があります。立てて収納すると全ての服に効果が得られます。
クローゼットやタンスに服をぎゅうぎゅう詰めにしない
ガスがいきわたるように、服の間に空気の流れができるように意識しましょう。収納ケースに入れるときは、いっぱいになるまで詰め込まず、少し隙間ができるくらいがベスト。
防虫剤の使用期限に気をつける
防虫剤はガスを発生させるものであるため、ある程度の期間が過ぎるとガスが薄くなってきます。取り換えのサインは色が変化したり、文字が浮き出てくることでわかります。使用期限が切れたものを使用し続けても効果は得られないので、衣替えのたびにチェックしましょう。
服の虫食いを防ぐために防虫剤を使用した後の注意

防虫剤を入れた後も油断はできません。定期的にチェックしたり、風を通して空気を入れ替えたりして対策します。
タンスやクローゼットを定期的に開けて空気を入れ替える
害虫は湿気のある場所を好むため、湿度の低い、カラッと晴れた日にはタンスやクローゼットを開けっぱなしにして空気を通しましょう。服が入ったままでも十分効果はあります。ただし、防虫剤のガスが逃げないよう適度に行う程度で大丈夫です。
虫干しする
衣服に風を通してあげることを「虫干し」といいます。これを行うことで湿気やかびを防げて、虫も寄り付きにくくなるんです。
天気のいい日に服をハンガーにかけ、風通しの良い場所で虫干しをします。直射日光は生地を傷めてしまう可能性があるので、日陰で行うと良いでしょう。2~3日晴れが続いた日の10~15時は湿度が低く、虫干しするのにおすすめです。
お気に入りの服が虫食いに遭わないよう日々の対策を忘れずに

ここまで、服の虫食いの対策法を紹介してきました。特に気をつけたいこの4点。
・湿度は敵!
・防虫剤は適切な使い方を!
・定期的に風を通す!
これを徹底すれば、虫は怖くありません。大事な衣服、穴が開く前にきちんと予防しましょう。
※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。
※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。
※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。
※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。