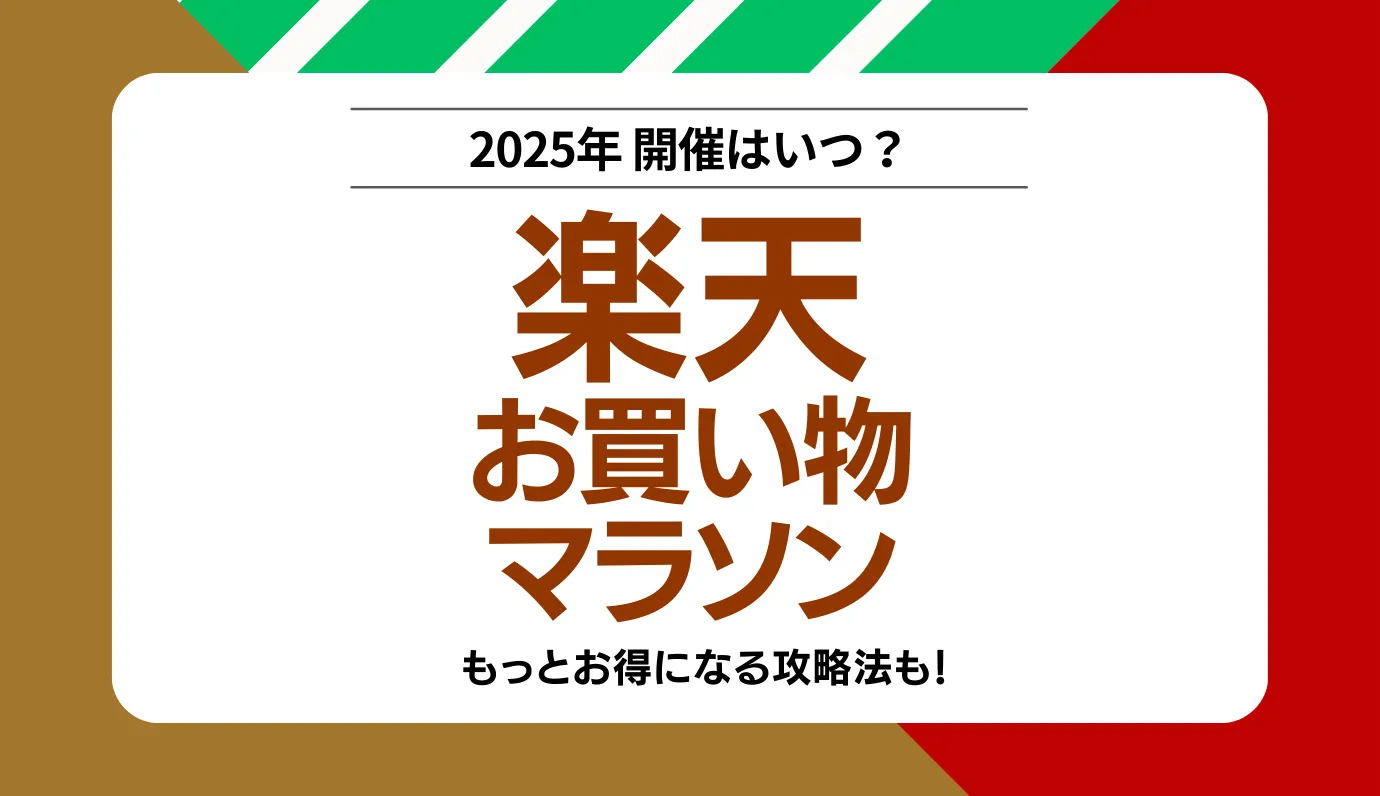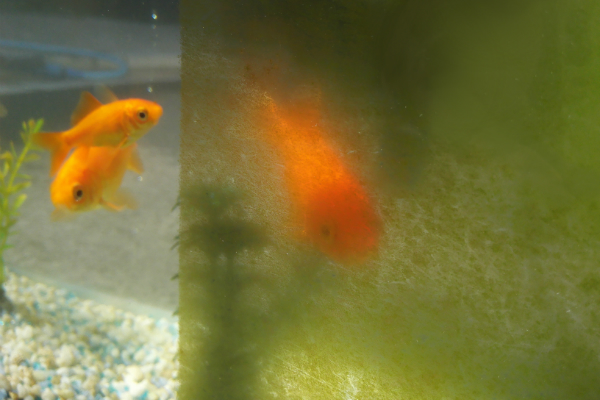
水槽の掃除は魚を入れたままがポイント!日頃のお手入れで汚れを防ぐ方法
熱帯魚を飼おうと思っても、水槽の掃除ってどうやってやるのか気になりませんか?水槽が汚れてしまうと、せっかくの魚の様子が見にくくなります。さらに放置すればするほど、コケやカビが生えてしまいます。しかも、水槽の中が不衛生だと金魚や熱帯魚が弱ってしまう可能性が。
そこで今回は、水槽につく汚れの種類、お掃除の頻度や方法を紹介します!
水槽の汚れの種類は?

常に水を入れた状態の水槽。カビやらコケやらをそのままにしていると、魚たちに悪影響を及ぼします。僕は昔、カニの水槽を放っておいて……。水槽をしっかり掃除するため、汚れの種類を知っておきましょう!命は尊いのです……。
水が緑色になる汚れ
ヘドロ状や膜状になっているコケは「藍藻(ランソウ)」です。シアノバクテリア(藍色細菌)とも呼ばれ、植物ではなく細菌の一種です。濃い緑色をしていて、水槽や水草を覆いつくしてしまいます。
藍藻は、成長スピードが速く、臭いや毒素を発生させる厄介なコケです。気がつけば水槽の中が藍藻だらけ、ということも多々あります。そして放置すればするほど掃除が大変に。
また、藍藻が繁殖したままでは金魚・熱帯魚に悪影響が及びます。水の流れが悪いことや生態系のバランスが悪いことが原因でしょう。見つけたらそのままにせず、早めにお掃除をしましょう。
水槽の壁に張りつく汚れ
水槽のガラスに付着する汚れは、コケの一種で「茶ゴケ・珪藻(ケイソウ)」と呼ばれます。水槽を買ったばかりで水質が不安定な頃に、表面に付いた汚れをエサに発生しやすいコケです。
原因は色々ありますが、主に生態系が不安定なことが原因だと考えられます。最初の時期を過ぎてからまた発生した場合は、生物のフンから出る物質に集まって茶ゴケが生まれています。
しかし、他の植物が同じ空間にいれば、時間が経つとほとんど発生しなくなります。植物プランクトンがいれば茶ゴケも生まれないので、日光に当てれば自然と消えるでしょう。
細長い汚れ
細長い糸になっているのが特徴的なのは「糸状藻(しじょうそう)」です。糸状藻の形状は育てている生物や水槽によってさまざまです。
ところ構わず引っ付きまくるので、取り除くには時間がかかる上、完全に取り除くことができません。特に、水草に付着したときはなかなか取ることができません。水の中ではまず無理。そういうときは、水草を丸ごと水槽から取り除くことになります。
こいつの問題点は、水槽の生態系が整っていても発生するところ!ということで言わせていただききましょう。防止は諦めて、と。
水槽を掃除するときの注意点

それでは水槽掃除をしていくのですが、先ほどお話したように「命は尊い」のです。
トイレや床の掃除とは違い、水槽はお魚たちのおうちですよね。いくつかのポイントを間違えると大変なことになってしまうのです…!水槽掃除を始める前に、注意すべきポイントを知っておきましょう。
換水のタイミングを意識する
水槽の水はどれくらいの頻度で入れ替えていますか?水が濁ってきたら、ゴミが浮いてきたらなど、人によってさまざまかもしれません。しかし、水槽内は私たちの想像以上に汚れていくんです!
例えばエサですね。食べ残しとなったエサは水を吸って沈み、砂利の中など水槽の底に沈んでいます。また、魚の体液なんかも原因ですよ!目には見えませんが、お魚はフン以外にも尿や体液を出しているのです。
交換の目安としては2週間に1回程度ですが、換水のタイミングは、まず意識したいポイントになりますね。
魚は水槽に入れたままが理想
キレイな水槽を保つための掃除だけれど、お魚がいてはやりずらい。バケツに移してから掃除をしている、なんて方は多いのでは?
しかし、考えてみてください。お魚にとって、掃除のたびに移し替えられるのはストレスになります!さらには移動のとき、身体を傷つけてしまうかもしれませんよね。
そして何より…正直言ってめんどくさいです!!そこで、ここは思い切って、お魚を水槽に入れたまま掃除をしてみましょう!水槽掃除用のスポンジを使って、そのまま内側をゴシゴシするだけです。ストレスを与えないように、やさしく掃除することが大切です。
日常的にやっていれば、お魚も慣れてくるそうですよ。汚れた水も、換水をすればキレイになっていくので問題ありません。
水は全部は入れ替えない
水の入れ替えは、お魚を飼う上で避けては通れない道ですね。時間をかけて、水をまるまる交換したなんて経験ありませんか?でも実は、水槽内の水は全部入れ替える必要はないのです!
お魚にとって重要なのは、水に適応していること。酸性アルカリ性を示すpHの値が大切なのです。すべて新しい水に換えられてしまうと、確かにキレイにはなりますがお魚は大変です。
お魚の負担を減らすためにも1/3程度の換水が理想!人と同じように住み慣れた環境の方がよいのです。
お掃除する頻度は適度に間を空けて
金魚や熱帯魚にとって環境の変化も大きなストレスになります。そのため、水槽が汚れていてもいけませんが、お掃除しすぎるのもかえってよくないのです。
水槽のお掃除には、主に、コケ・砂利・ろ過槽のお掃除と水替えの作業があります。それぞれを一気に行うのではなく、短くても1週間ほど、通常だいたい2週間から1ヵ月ほど空けて別々にお掃除をすると良いです。期間を空けると、環境の変化を最小限に抑えられます。
とはいえ、なるべくコケが繁殖しないように、また水質が汚くならないように工夫をしていくことが重要。次の3つを日頃から気をつけておきましょう。
・直射日光が当たらないところに水槽を置く。
・水槽に水や魚、水草、エサを入れすぎない。
栄養が増えすぎてもコケが増えるってのがなんとも面倒ですね。しかし、常にキレイな水槽を維持することは、大切な金魚や熱帯魚のためになりますよ!
コケのお掃除の方法

まずは、コケのお掃除を楽にするアイテムとお掃除の方法を紹介していきます。
コケの掃除とひとくちに言っても、ガラス面や石・装飾品などコケがつく場所はさまざまあります。それぞれによって、コケの掃除方法が違います。そこで、ガラス面と石・装飾品に分けて紹介します!
コケのお掃除におすすめのアイテム
コケのお掃除を楽にするアイテムを2つ紹介します。
かき取るタイプ
おすすめ
[PR]

おすすめ
[PR]

コーナー・ガラス・パイプと場所ごとに分けてコケを取ることができます。気持ち良いくらいにコケが取れるので、ぜひ普段のお手入れに試してみてください。さっと潜らせれば取れますので。
設置するタイプ
あまりにコケが多い場合には、こちらも使ってみてください。
おすすめ
[PR]

魚類に影響がない薬品です。コケが栄養とするアンモニアを減らし、大量に発生するのを抑制してくれます。
ガラス面のコケの取り方
ガラス面のコケに最初に気づくのではないでしょうか?中は見せないぞとばかりに自己主張する正面のガラスはもちろん、コケで汚れたガラスの全面をお掃除しましょう。
ただし、ガラス面についている汚れの中には水質をキレイにしてくれるプランクトンが含まれていることもあります。鑑賞するときに見た目が気にならない程度に汚れが落とせていれば十分です。
先ほど紹介したようなスクレーパーでかき取っていきましょう。こびりついてしまったコケにはおすすめです。その他にもシートタイプやメラミンスポンジタイプのお掃除アイテムもあり、コケを拭き取っていくという方法もあります。
お家の水槽の汚れ具合に合わせて、いくつかのアイテムを試してみてください。
石や装飾品のコケの取り方

石や装飾品を水槽内でのレイアウトを崩さないように掃除するには、動かさずにその場所でブラシで磨くしかありません。しかし、それでは頑固なコケを落とすことはできません。
細かなところまで磨けるマーナ 掃除の達人すみっこブラシ 「掃除の達人」をオススメします。
おすすめ
[PR]

水槽用のグッズではありませんが、角度のついたVカットブラシが特徴的な商品です。汚れをしっかり落としたいときには、水槽から取り出してゴシゴシこすり洗いしましょう。歯ブラシなんかを使ってもいいと思います。
砂利・ろ過槽のお掃除方法

それでは続いて、砂利のお掃除を楽にするアイテムとお掃除の方法、ろ過槽のお掃除の方法を紹介していきます。
砂利のお掃除におすすめのアイテム
まずは、砂利のお掃除を楽にするアイテムを紹介します。
おすすめ
[PR]

砂利はそのままで、水替えをすることや金魚や熱帯魚の排泄物を取り除くことができます。要するに“デカいスポイト”ってことです。
砂利のお掃除の方法
砂利は、汚れているのが見えづらいため、ついお掃除するのを先延ばしにしてしまいますよね。表面に汚れが目立ってきてからお掃除を始める方も多いと思います。
砂利の表面は、水槽に生息する生き物がキレイにしてくれていることがあります。では一体、砂利の中の方はどうなるのかというと、フンや残ったエサなどがだんだん入り込んでいくのです。…こわいこわい。
砂利の奥に溜まった汚れは水に溶け出し、水自体を汚してしまいます。というわけで、砂利の中をお掃除することが大切なのです。
水を替えずに掃除をするときには、先ほど紹介した専用のアイテムを使って、砂利の中の汚れを吸い取っていきましょう。
水替えと同時に掃除をする場合は、ボウルに砂利を移して水槽の水を使って洗いましょう。
水道水ではなく水槽の水を使うことで、砂利を水槽に戻したときに環境の変化を少なくすることができます。
ろ過槽の掃除について
ろ過槽が詰まると、ろ過能力が落ちてコケの発生が早くなってしまいます。水質が安定しない場合などは、ろ過器を中心にもう一度、水槽の状況を見直してみてください。大きめのろ過器を買うことも検討してみてはいかがでしょう。
ろ過装置にも、水槽の環境を良くしてくれる生物がいます。そのため、ろ過装置を掃除するときにも水槽の水を使うといいです。フィルターの目に詰まった汚れを取り、容器に移した水槽の水ですすぐくらいで十分です。
ろ過槽をお掃除している間は、フィルターの電源を切らなければいけません。そのため、あまり時間をかけることなくサッと掃除を終わらせることが大切です!
水替えの方法

わたしたち人間にとって「空気」が大事なのと同じで、魚にとっては「水」がとっても大切なんです。
水槽のサイズや魚の量、ろ過器の大きさなど、水の汚れ方によって頻度が大きく変わりますが、一般的には「2~3週間」に一度、「約3分の1程度」の水を交換しましょう。
魚は環境変化が大きいと、ショックで病気になったり、死んでしまったりします。ですので、水の交換もこの頻度と量を守って行ってください。
・水をすくうカップ または 水を吸い取るホース(水作プロホースなど)
・カルキ抜き剤・ヒーター
おすすめ
[PR]

水道水は、魚や水草にとって有害な塩素が含まれています。この中和剤などのカルキ抜き剤を使用して、熱帯魚にとって有害な物質を除去しましょう。
おすすめ
[PR]

水を交換した際に、水温があまりに変わると魚にとって好ましくありません。ショックで寿命が縮まるのを防ぐために、こういったヒーターを使って水温を一定に保ってください。

すべての機材の電源をオフにするか、コンセントを抜きます。

カップで水をくみ取るか、ホースを使って砂利を掃除しながら、水槽全体の1/3ほどの水を抜いていきます。
抜いた水は捨て、ヒーターを使って水槽の温度に合わせた水道水を用意します。カルキ剤をでカルキ抜きをして、塩素を中和してから水槽に入れていきます。

水替えが終わったら、機材を一つ一つ確認しながら電源を入れ、終了です。
水槽の汚れを防止する工夫

最後にそもそも水槽の汚れを防止する工夫をご紹介します。
水替えを定期的に行う
金魚は胃がなく排泄物が多いため、汚れがどんどん蓄積されていきます。水温や水槽の大きさにもよりますが、冒頭の頻度で触れたように基本的に2週間から1か月に1回を目安に水換えをしましょう。
コケを取る生き物を入れる
コケを食べてくれる生き物を入れるのもオススメ。掃除すると見た目はきれいになりますがバクテリアも減らしてしまいます。小さいエビや貝類などコケをエサに生きるコケ取り生物を入れると、汚れるスピードがぐんと下がります。
エサを入れすぎない
エサを多く与えると排泄物が増えて水質悪化が進んだり、食べきれず残ったエサが水中に溶け出して、水に含まれる栄養分が増えすぎて汚れます。体の大きさにもよりますが、エサは数分以内で食べ切れる量にしましょう。
まとめ

魚が健康に生きて行くためには、定期的なメンテナンスが必要ということがご理解いただけたかと思います。面倒くさがらずに、手順をきっちり守って、道具をしっかり揃えて掃除を行なってください。
また、水槽の中だけでなく、周辺の手入れも必要になってきます。熱帯魚の場合は、ろ過器・照明・ヒーターなども使うと思いますが、そのコンセントの掃除もしてください。掃除を怠っていると、ショートしてしまうかもしれませんよ!
※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。
※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。
※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してださい。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。
※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。